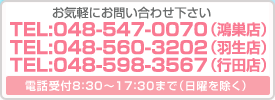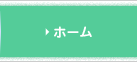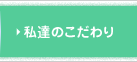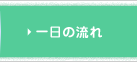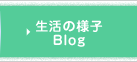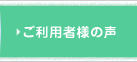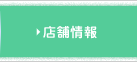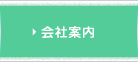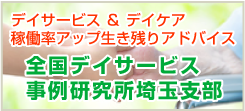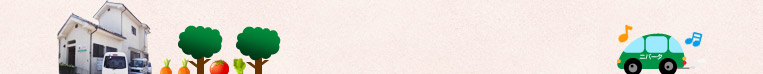「知的所有権」という言葉・・・
現代社会において、知的財産権の重要性はますます高まっています。発明や著作物など、人々の創造性によって生み出されたものを保護するこの制度は、文化や産業の発展に大きく貢献してきました。しかし、近年、その保護の範囲が広がりすぎ、本来の目的から逸脱しているのではないかという懸念の声も上がっています。
特許期間の過度な延長や、些細なアイデアに対する権利付与の増加。著作権においては、デジタル技術の進化に伴い、保護期間が長期化し、二次利用のハードルが高まっています。このような状況は、新たな創造活動を阻害し、文化的な交流や発展を停滞させる可能性があります。
本来、知的財産権は、創造者の権利を守りつつ、その成果を社会全体で共有し、さらなるイノベーションを生み出すための仕組みであるはずです。しかし、過剰な保護は、まるで独占権のように機能し、後発の参入を困難にし、自由な発想や競争を抑制する要因となりかねません。
まるで、せっかく生まれたアイデアの芽を、権利という名の巨大な壁が覆い隠してしまうかのようです。創造の源泉である自由な発想や、過去の遺産の上に新たなものを築き上げるという文化的な営みが、過度な権利意識によって阻害されるとしたら、それは社会全体の損失と言えるでしょう。
知的財産権の適切なバランスとは何か。それは、創造者の正当な利益を守りながら、社会全体の発展を促すことができる範囲にあるはずです。今一度、そのあり方を見直し、創造の灯を絶やすことのない社会を目指すべきではないでしょうか。